交通系ICカードがスタートして20年ほど経ち、電車でもバスでも「大体どこでも使える」感がありますよね。地方都市でも中心部では使用できる交通機関が増えています。
普段の生活に交通系ICを使うことがない方でも「使えるエリアに行く時に便利だから」という理由で所持している方も多いのではないでしょうか。(最近はスマホアプリのモバイルICが主流?)
ところが最近、「QRコード」の切符や、クレカをタッチで乗車する仕組みの導入が進んでいるようです。これってどんな理由??

ある程度スタンダード化した交通系ICがあるのに、なぜ今、新たな「QRコード」の切符や、クレカで乗車の仕組みが増えてるのか、気になっていた方多いのではないでしょうか?
今年(2025年)に入って、JR西日本でも「2028年以降、近距離の普通乗車券の発行を、磁気券を縮小してQRコードへ順次移行する」との報道がありました。
⇒ JR西日本、磁気切符をQRコード移行 28年以降に(日経新聞WEB)
2025年現在、磁気切符の主な役割は、交通系ICを持たない方、交通系ICが使えないエリアに行く方に使われています。そのため、カンタンに廃止にすることは出来ず、この役割の代替として「QRコード」切符が増えているようです。
磁気切符はスタートして50年以上が経過し、全国に普及したシステムではありますが、実は何かとコスト高。。。
最近になって注目される、回収した磁気切符の処理(分別)のコスト。
環境への配慮はスタンダードになり、分別処理やリサイクルへの対応は必須。ですが、磁気切符には金属成分が含まれているので、「紙」と「磁気部分」の分離が難しい、、、。そのため、処理のコストが高くなるのです。
既に普及している改札機ですが、この維持費(メンテナンスや更新費)が結構かかるという問題があります。
磁気切符の改札機。よく紙詰まりを起こしてるイメージってありますよね?
業者の方が修理しているシーンにも度々遭遇します。
そもそも、改札機に切符を通して読み取る仕組みなので、ハード的に摩耗もしやすく故障も増えます。機器のメンテナンスには、現場で作業する人件費もかかりコストが高くなるのはやむを得ないですね。
QRコードはそもそも紙に印刷する必要もなく、スマホ画面に表示させて使用できます。
切符の回収も処理も不要です。
また、QRコードを紙媒体に印刷して使用する場合でも、複雑な分別は不要で、処理コストを格段に下げることが可能です。
「QRコード」の読取りはカメラ式です。
以前にもホームドアの記事でご紹介しましたが、カメラの性能が上がり、またカメラ自体も安価になったことで、QRコードを読み取るリーダも安価になりました。
⇒ QRコードでホームドアが開く?!これってどんな仕組み?なぜQRコードなの?
現在の改札機にQRコードを読み取るリーダ(カメラ)を設置するのは、比較的安価に導入が可能でしょう。また、カメラのリーダは、切符がカメラ部分に直接触れることはないので故障のリスクも低いと考えられます。
確かにQRコードは「画像」なので、カメラで写せば簡単に複製可能がです。
ただ、システム上で「一度使用されたQRコードは使えなくなる」ように出来るので、悪用されるリスクは格段に減ります。
「複製による悪用」は、おそらくQRコード導入の際に一番懸念されたであろう点なので、対策はされているのではないでしょうか。
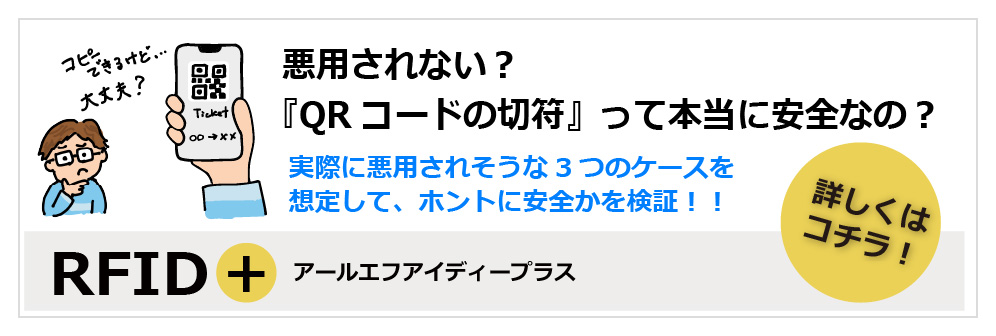

これも、現在の主な理由は交通系ICを持たない方への対策のひとつ。
観光客や出張の方、外国からの旅行者の方の利便性の向上が主な理由です。
また、クレカでの乗車は海外ではメジャーな乗車システムなので、海外の方でもスムーズに利用可能なのも理由のひとつです。
ただ今後は拡大の予感を感じさせるクレカでタッチ乗車。
主なメリットは、①事前登録不要 ②チャージ不要
ICを発行する交通機関側の事務コストは下がり、交通系ICのチャージシステムや機器も不要になります。
クレカでタッチ決済の仕組みは、今後のコスト削減にかなり有効といえます。
現在既に普及しているシステム(仕組み・機器)も、周期的に更新の時期を迎えます。
今後コスト削減につながるシステムは、そういったタイミングで切り替わっていくのかも。
実際に、多くの交通機関が導入を進めているようです。

ほとんどの交通機関では、交通系ICカードの利用はそのまま継続とされています。
現時点(2025年)では、QRコード切符もクレカでタッチも、主に「磁気切符」からの移行手段として導入が進んでいるといえそうです。
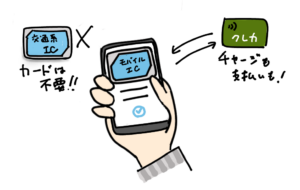
交通系ICは、金額の違う通学用定期や通勤用定期、特定区間での割引などの複雑な料金体系を利用者毎に対応させています。
この複雑な設定は、クレジットカード側で設定(反映)するのは容易ではないため、交通系ICは(縮小はしても)今後も継続されるでしょう。
交通系ICは、縮小・廃止するのではなく、ICカードからモバイルアプリに移行を推進し交通系ICのメリットを最大限に活かす方向に進んでいます。
モバイルアプリであれば、アプリにクレカを登録することで「タッチ乗車」が可能です。
ICカードではなくモバイルアプリであれば、コスト高と言われる「チャージ用の機器」も不要。設置台数を削減することができます。
多くの交通機関で、利用者の利便性を向上させつつ、コストの削減を目指しています。
現時点での主流が、10年後にどうなるかは未知数ですが、事業者だけでなく、利用者にとってもメリットのある方法が今後主流となっていくことでしょう!
これは、決済方法を出来るだけ集約しコストを抑える(機器の更新費用、メンテナンス費用などの維持コスト)というのが主な理由のようです。
全国交通系ICの利用を廃止する動きは、地方の交通機関で見られるようです。
利用者の数が多くない交通機関ほど、複数の決済方法はコスト高。地域に適した方法に絞るのも選択のひとつです。